ジェネシャリスト診断学 その2 スペシャルに考える(岩田健太郎)
連載
2015.07.06
The Genecialist Manifesto
ジェネシャリスト宣言
「ジェネラリストか,スペシャリストか」。二元論を乗り越え,“ジェネシャリスト”という新概念を提唱する。
【第25回】
ジェネシャリスト診断学 その2 スペシャルに考える
岩田 健太郎(神戸大学大学院教授・感染症治療学/神戸大学医学部附属病院感染症内科)
(前回からつづく)
医者にとって極めて重要な把握観念は,「時間の観念」である。時間の観念把握に優れた医者は診断戦略に優れており,時間の観念に鈍感な医者は有効で戦略的な診療ができない。この話は『構造と診断――ゼロからの診断学』(医学書院)にまとめた。悲しいかな,多くの医者は時間の観念に鈍感である。その話は『1秒もムダに生きない――時間の上手な使い方』(光文社)で詳説した。
宣伝ばかりしていても埒(らち)が明かないので,本題に入る。ジェネラリストの多くは「前医」である。「後医は名医」=「前医は名医ではない」のは,結果としてそうなっているのではない。そうあるべきだから,そうなのだ。フォワードが全てのボールをカットしたりしないよう,前線では「ほどほど,見逃す」くらいがちょうどよい。そう前回(第3129号)で述べた。
そのようなプラクティスの正当性を担保しているのが,時間性である。前医・後医という言葉の使い方がすでに「前後」という時間性を内包している。
*
多くの疾患は即座の診断を必須としない。どんな慢性疾患にも必ずオンセットというものがあり,全ての慢性疾患も最初は急性疾患(発症からの時間が短い)なのだが,オンセット直後に慢性疾患を診断することは極めて困難で,そしてその必要はない。最初は風邪だと思っていたのに,実はリンパ腫だった。最初は肩こりだと思っていたのに,実は関節リウマチだった。最初は単なる疲労だと思っていたのに,実は筋萎縮性側索硬化症(ALS)だった――。この「最初」の時点で,こうした疾患全てを想起し,また精査しなくても,後からゆっくり診断すればよいのである。もちろん,ゆっくり過ぎるのも問題で,いたずらに患者を長らく苦しめる必要もないから,ここでも「時間性」は重要なのだが。
悪性疾患のオンセットは患者本人にも感じ取れない。もっと言えば,多くのがん細胞は自分の免疫細胞で処理されているだろうから,多くの「オンセット」は「オフセット」になってチャラにされてしまう。そのようなオフセットにされる事象を「がんだ!」と見つける術があったとして(ないけど),それは無意味な作業である。がんの早期診断=スクリーニングが必ずしも有効な手段とは言い切れないために,今も前立腺がんや乳がんの検診問題はもめにもめているわけだ。
もちろん,最前線で見逃せない疾患もある。“超急性疾患”で,ここで拾い上げておかねば患者の命にかかわる,という場合だ。心筋梗塞然り,くも膜下出血然り,大動脈解離然り,細菌性髄膜炎然り,壊死性筋膜炎然り(こうして見ると血管の病気と感染症が多いのに気付く)。甲状腺クリーゼや急性白血病も見逃したくない。しかし,こうした疾患群を初診で見逃さないために必要なスキルもまた,「時間性」を念頭に置いている。
時間性を自家薬籠中の物とすれば,見逃せない超急性疾患(あるいはその疑い患者)を十分に拾い上げ,かつ「見逃しても差し支えない」患者を戦略的に見逃すことができる。
超急性疾患疑い患者は,速攻で後方のスペシャリストにパスする。「見逃しても差し支えない」患者の場合は,再診時に後方にパスされる(あるいは自ら診断する)。これがチーム医療の枠内での前線の医者の在り方だ。プライマリ・ケアとはサッカーにおけるフォワードみたいな存在なのだ。普通は逆に考えられがちだが……。
*
もう少しサッカーのアナロジーで言うと,フォワードが寄せて前線からプレッシャーをかけていると,相手のパスコースは限定される。よって,たとえフォワードがカットできなくても,ボールの来る方向はかなり予見できるようになる。「開業医に診てもらってもなかなか診断がつかない熱」という時点で,それは『ドクターG』的,診断カンファレンスのネタになりそうな疾患にかなり絞りこまれていることを意味している。こうしたカンファレンスで,やたらと「血管内リンパ腫(IVL)」と連呼されるのはそのためだ(超まれなのに)。
後方の医者(スペシャリスト)は,コストや時間のかかる検査の連打を正当化できる。「熱」に対して行い得る検査は山のようにあり,全ての発熱患者にそれをやるのは無理筋だ。しかし,「不明熱」=前線で診断がつかなかった熱に対して,ブルセラ症の抗体検査をオーダーするのは,リーズナブルな判断である(かもしれない)。繰り返すが,「後医は名医」なのは単に現象的にそうなのではなく,構造的にそう振る舞うべきなのだ。
まれな疾患の成れの果ては,「存在しない病気」だ。病名は現象に対してつけた名前だ。多くの現象には,名前がまだついていない。そうした病気を新しい疾患概念として提唱するのも大切な後医の仕事である。そこには,前回述べたような研究的な要素も加味される。
*
もちろん,サッカーがそうであるように,前線は前線,後衛は後衛と役割分担を硬直的に決め付ける必要はない。プライマリ・ケアのセッティングで新しい疾患概念を提唱したっていいし,スペシャリストが先鋭的な自分の専門外領域をカバーしたっていい。要は患者ケアが結果的にうまくいけばよいのであって,システムは手段であって目的ではないのである。
このように,診断戦略は目的から逆算し,セッティングから逆算して,帰納的に決定される。正しい,一意的な診断戦略は存在しないのである。診療のセッティングが変わったとき(異動のとき),誤診が増えるのもそのためだ。
よって,「病歴と身体診察派」と「検査派」のような二元論は全く無意味,ということになる。プライマリ・ケアのセッティングで検査を乱用するのは,前線のフォワードが守備に走り回るのと同じで,目的から逆算して合理的ではない(そのような“汗かきフォワード”を褒めたたえる日本のサッカー評論家はなんとかしてほしい)。後衛のスペシャリスト的アプローチが絨毯爆撃的検査の連打になるのは,多くの場合は当然であり,まれな疾患,まだ名もない疾患をほじくりだすには合理的な選択肢なのである。
もちろん,診断は魅力的な営為であり,そこには“お色気”の要素がある。「普通の高血圧」から褐色細胞腫を,「普通の腹痛」から鉛中毒や急性間欠性ポルフィリン症を拾い上げてやりたい,という欲望を持たないプライマリ・ケア医は,いかにもつまらない。なので,時には欲望に身を任せるのも悪くない。もちろん,いつも欲望にカラれるばかりの色ボケ爺になってはダメなのだけど。
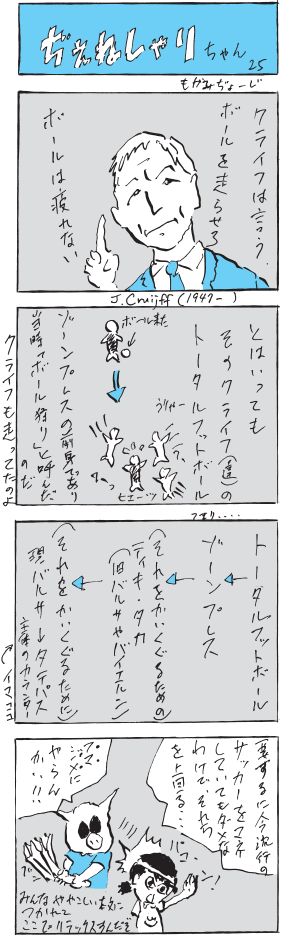
(つづく)
いま話題の記事
-
忙しい研修医のためのAIツールを活用したタイパ・コスパ重視の文献検索・管理法
寄稿 2023.09.11
-
人工呼吸器の使いかた(2) 初期設定と人工呼吸器モード(大野博司)
連載 2010.11.08
-
連載 2010.09.06
-
事例で学ぶくすりの落とし穴
[第7回] 薬物血中濃度モニタリングのタイミング連載 2021.01.25
-
寄稿 2016.03.07
最新の記事
-
医学界新聞プラス
[第3回]人工骨頭術後ステム周囲骨折
『クリニカル・クエスチョンで考える外傷整形外科ケーススタディ』より連載 2024.04.19
-
医学界新聞プラス
[第2回]心理社会的プログラムを分類してみましょう
『心理社会的プログラムガイドブック』より連載 2024.04.19
-
医学界新聞プラス
[第1回]心理社会的プログラムと精神障害リハビリテーションはどこが違うのでしょうか
『心理社会的プログラムガイドブック』より連載 2024.04.12
-
医学界新聞プラス
[第2回]小児Monteggia骨折
『クリニカル・クエスチョンで考える外傷整形外科ケーススタディ』より連載 2024.04.12
-
医学界新聞プラス
[第5回]事例とエコー画像から病態を考えてみよう「腹部」
『フィジカルアセスメントに活かす 看護のためのはじめてのエコー』より連載 2024.04.12
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
